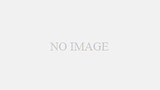こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
落花生の季節も終わりました。
かつて、私の子ども時代は生の落花生もピーナッツと呼んでいたものでした。その後、千葉など産地の農家さんたちから「落花生と呼ぼう」という呼びかけがありました。今では加工されたものだけがピーナッツで、生の状態は落花生と呼ぶのが定着したようですね。野菜の名称・呼称は時代とともに変わるものです。
ちょっと余談ですが、数年前に亡くなった故・ジミーかーた元米大統領は、出身がピーナツ農場主だったと聞いています。日本人からすれば「ピーナッツ農場の主でも大統領になれるのか」と思ったことでしょうが米国ではピーナッツの需要は日本とは桁違いで、だからこそ絶対外国からピーナッツを輸入することはない。日本がかつて「一粒たりとも米を輸入しない」と言って米国からフェアでないと攻撃されましたが、それを言ったら米国とて、保護しているものは色々あるわけです。閑話休題。

「花から落ちて生きる」という名は、実際に落花生を育ててみて驚く方も少なくありません。
収穫のタイミングは、他の豆と同じように、農家さんのレベルでは絶妙なタイミングがあるのでしょうが自給菜園ではそれよりも掘り上げた新鮮なものを茹でてからの加減の方が大事かも。
塩茹でする時間が20分以上かかりますが、茹で過ぎてもいけないし、その辺の加減は、ちょこちょこつまみながら、頃合いを見る。
余程たくさん取れたらピーナッツバターも贅沢な楽しみですね。水飴など混ぜない、塩だけの本物。

三枚目の写真は落花生の根。
根っこのツブツブが「根粒菌(こんりゅうきん)」です。
空気中の窒素分子はとても安定していて植物は吸収できないので、それを植物が吸収できる「アンモニア態窒素」という化合物に「両替え」してくれる大事なエージェント。
日本語では菌という名称で、色々な微生物をひっくるめていますが、いわゆる「菌ちゃん」で有名になっている糸状菌はカビやキノコを含む真菌類の仲間です。
こちら根粒菌は細菌類ですから、かなり違いますね。
「自然農を学ぶ・さとやま農学校」の収穫も、こうして炭水化物の作目が増えてきました。
冬に備えて野菜たちも太り出したところ。それを食べてしまう我々動物は、つまり自分では光合成も何もしないで栄養分を頂いてしまおうという魂胆だから、なんだかちょっとずるくもあります。
「さとやま農学校の見学会・お試し体験」にどうぞ。
さとやま農学校って、どんなところ?
自分に通えるのかなあ?
…ごく自然なお気持ちですね。
どうぞ、まずは現場においでください。
12月3日までは授業の実際を見学できます。
それ以降は年末まで、簡単なお試し体験ができます。
どちらも無料です。
1月以降も見学会はありますが、やはり風邪をひく方が多いので、
できるだけ年内においでいただくことをお勧めします。
そして、ご入会は随時できます。
冬は、春に備えての畝づくりや炭焼き、剪定、エコロジカルなデザインなど、盛りだくさんです。
既に畑を始めているけれど、上手くいかないという方も、基本からブラッシュアップしましょう。
まずは、一歩を踏み出しましょう。
詳細とお申し込みは下のリンクからどうぞ。