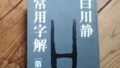こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
今年も、古代赤米が登熟してきました。
国分寺で育てられてきたものを相模湖に分けて頂いてから、もう6年になります。
「自然農を学ぶ・さとやま農学校」で育てているものは、小さな樽に入れたもの。
いわばバケツ苗ですが、健やかに育っています。
この暑さでも、実に強い。
7月下旬の出穂を経て、だいぶ登熟してきました。
自分を守るための「禾(のぎ)」がツンと長いのも特徴です。
ただし人間がコメを食べるためには、禾があると邪魔なので、今のコメにこんな長い禾はありません。
しかしご覧のように、熟している度合いが、粒によって、あるいは穂によってまちまちです。
しかも熟したものからポロポロと脱粒します。
これが現代のコメのように一斉に熟してしまうと、台風や鳥獣害のときに、一斉に壊滅するリスクもある。だからタイミングを分散させて熟すのです。
あるいは翌年の発芽もばらつきます。
自然界で種を残すためには自然なことです。
ところが、それでは人類にとっては面倒です。
しかもポロポロ落ちてしまっては、泥まみれのモミを鳥や虫と競い合って拾わなければならない。
ということで、改良に改良を重ねて今のように登熟が揃い、かつ熟しても脱粒せずに穂が垂れ下がったままのお米になりました。この脱粒性の克服が、人類にとっては非常に大きなもので、例えば古代小麦の「スペルト」などは、やはりポロポロと収穫の時に脱粒します。スペルト小麦にしてみれば当然の抵抗・逃亡でしょう。でも食べる側にしてみれば「もったいない!」となる。
こうしたやり取りを長い歴史の中で繰り返してきたのが農業です。
野菜も穀物も、大なり小なり、人間が野生のイキモノを飼いならしたものです。
これを馴化(くんか・Domestication)といいます。
「古代~」と名がつくとロマンな響きがありますが、なかなか手間はかかるものです。
しかし、しかし、です。
効率化を求めて人類は今に至るのですが、その効率化は、返す刀で人間もまた効率似合わないものを切るり捨てつつあります。どんな野菜よりも、いちばん不揃いなのが人間ですから。
その生きづらさ、息苦しさは、とりわけ若い人。・次の世代の人たちにしわ寄せが行っているように感じます。せめて、土の上では、効率ばかり追い求めずに、色々なイノチが循環して支えあう様子を感じて欲しいものです。
自然農は、イノチのやりとりを感じる場です
農とは人間界と自然界の「命のやり取り」です。
自然農では、一方的に人間が食べることばかりでなく(もちろんそれは大事なことですが)、色々なイノチが巡る様子も感じながら手を動かします。
「さとやま農学校・秋のショートコース」は9~12月のコースと12月~来年1月までのコースがあります。9月に間に合わない方も10月から参加できますよ。まずは農への入り口においでください。
土曜と火曜の2コースあります。
詳しくはHPをご覧ください