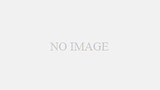こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
自給の自然農を学ぶ・さとやま農学校の皆さんとハクビシン・アライグマ対策の電気柵を設置しました。
さとやま農学校の皆さんと、午前中の作業でした。
なにしろここは、森とせめぎあう最前線なので、気を緩めると大変なことになります。でも鳥の声をBGMに手を動かすのは気持ちよいですね。微妙な風が感じられるくらいのスピードでゆっくり動くのが心地よかったです。
写真は、埼玉県の農林総合研究センターさんが開発された「白楽くん」と呼ばれる仕掛けです。ハクビシンやアライグマの、フェンスでも何でも登れる性質を逆手に取ったものです。上の方に電気が通っているので、地面から草が伸びて漏電する心配がないのです。
今は都内でも民家の屋根裏にハクビシンが棲むほどの時代になりました。愛情こめた作物を守る方法として、これは有効と思います。
それと温暖化が進んだおかげ(?)で、いまトウモロコシを蒔いて10月に食べられるようになりました。遅まきによって、アワノメイガの発生サイクルを回避できます・・・とはいうものの、連中も温暖化の影響で発生サイクルが大きく変わる可能性もありますね。水田ではすでにイナゴも出て、植えたばかりのイネを食べているとか・・・。
後はカラスの対策をして、守って守って・・・食べていくための仕事はキリがないですが、本来の生き物はヒトも含めて、生きている時間のほとんどを食べることに費やしているものです。
生まれて食べて死ぬ。シンプルですね。
皆さんも是非、料理でも味噌づくりでも野菜づくりでも、田んぼのお手伝いでも、なんでもいいから、食べるための時間を増やしましょう。


トウモロコシの大敵アワノメイガの対策も必要です。アワノメイガの進入路になる雄しべは、実が着いたら(受粉したということなので)切ります。
スズメバチを誘引するのと同じようなトラップも有効なようですので、これも試してみようと思います。


ひっそりと静かな日中

ズッキーニは小さいうちに収穫するのが美味しい。

自家採種のカボチャ(ハッパード)も元気に伸びてきました。
ツルがネットの外に逃げ出さないように誘導します

こちらは先週開催した「自然農のプランター栽培講座」の1回目です。
永年のお付き合いの国分寺カフェスローさんにて。
これはまた改めてご紹介しますが、プランター栽培は、この先の猛暑でもますます大事になってきます。ただし都会でプランター栽培をするのは、自然のバランスが「ない」中でのデメリットもついてきますね。でも逆に言えば、人間が、どれだけ普段自然と切り離された暮らしをしているのか気づく機会にもなります。
おかげさまで、既に二回目7月の講座も満員になりました。
8月はまだ参加できますが、おそらく満員は必至なので、お早めにお申し込みください。
今申し込んでいただければ、6月や7月の様子もフォローできます。また参加者限定のページで、情報も共有できます。