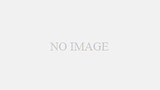こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
「自然農を学ぶ・さとやま農学校」で古代赤米を刈り取りました。
古代赤米を刈り取りました。
今年はささやかにバケツ稲です。
他の草木の合間で、健やかに育ってくれました。暑い中お疲れ様。
一枚目の写真にあるように、古代のコメは、ポロポロと脱粒します。それは自然界では当然のことで、植物はこうして種をこぼすことで子孫を増やします。2枚目の拡大写真は、ツンと伸びた禾(のぎ)です。虫や鳥から身を守るためですが、これもヒトには邪魔。
そこで、長い年月をかけて、こぼれにくい米、禾の短い米に改良してきました。
こうして1万年ほど、効率が良くて収量の多い穀物を作り続けて、ヒトは飛躍的に人口が増えた、文明が始まった。というのが定説です。
しかし。

コメやムギが世界中で作られるようになったのは、支配する側に都合が良かったからではないか、というのが「反穀物史」を著したジェームズ・スコットの説です。地球上にはおびただしい作物があるのに、コメやムギばかりが多すぎる。と。
ユヴァル・ノア・ハラリの「サピエンス全史」は、さらに俯瞰して、コメやムギが人類を「利用して」自分たちを増えるようにしたのではないか、とも書いています。ミトコンドリアが人類を操作したSF小説「パラサイト・イブ」を連想します。地球上に満ちるコメやムギは、人間と「共利関係」にあるのだというわけです。
実際にコメでもムギでも作って思うのは、穀物を育てて収穫して、蓄えるという一連の行為には、厳密なルールが必要です。ちょっと芋を植えて食べるのとは訳が違う。
だから集団もできて、いずれムラになり、クニになる。そこには蓄えの差もできる、つまりは貧富の格差もできて、さらに蓄えを巡って争う。それは米や麦の源泉としての土地や水の争いにもなる。
秋空の下の収穫は晴れがましく、心からありがたいものです。その一方、ヒトが何千年も営々と続けてきたことの意味も、考えてしまうのですね。
本やネットでアレコレ論じるよりも、まずは少しでも、何かしら育てて収穫して(あるいは失敗して)、ヒトであることの意味を感じてみるのがいいと思います。それこそ、大人も子供も一緒に。
生ゴムみたいな不定形の情報空間に沈まないためにも、身の程で世界を考えることは必要です。
ゆっくり秋から自然農を始めましょう
初心者の方には、とても入りやすいコースです。
あと2週間で10月からのコースも始まります。
お申し込みの枠はわずかとなりました。
同時に「さとやま農学校・本講座」も若干名の参加枠があります。
移住を考える方や、じっくりと自然農を学びたい方には、こちらがお勧めです。
初心者にとっては、秋は春よりも農業を始めるには理想の季節です。
ゆっくりと土と対話できます。
夏の疲れが、秋空の下で癒されます。
まずは「さとやま農学校の見学会」においでください。
現場の様子をご覧いただけます。