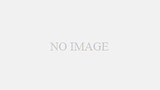地元の津久井在来大豆の自然栽培。
「自然農を学ぶ・さとやま農学校」の皆さんと一緒に、最後の追い込みです。
種の直播きはしていません。
すべて「断根摘心」で育苗したものを定植しているのですが、定植時期の微妙な違いで生育がだいぶ違うのが、非常に勉強になります。そこが難しいと言えば難しい。
津久井在来は在来大豆なので、一般的な育成品種(多くは国や都道府県が育成した品種)と違って蔓化(まんか)しやすい。いわゆる「ツル呆け」です。茎葉が繁茂しすぎる反動で実が入らない。
そのための対策として、播種期の厳密な設定や、土壌を肥沃にしすぎない事、などがあります。
しかし昨今の温暖化や空梅雨で、これまでの農事暦はあてにならない。そして自然農・不耕起の場合は、年々土壌が豊かになるので「大豆は痩せた土地を好む」などと言われても困る(笑)。
そんな諸々を前提として津久井在来大豆を育てています。
いずれにしても、いまのところ故・岩澤信夫先生の提唱された「断根摘芯栽培」は、今年の猛暑と空梅雨のなかでも、定植のタイミングさえあえば、土寄せも最初の一回だけで済むし、非常にありがたいものです。
さてさて、あと一か月足らずで、どこまで行くでしょうか。祈る気持ちで「さとやま農学校」の皆さんと大豆の畝を検分しています。

この畝は、だいぶ出来上がりました。
ここまで来ればだいぶ安心です。



ご覧のように、まだ下葉に緑が残っています。
この時期の大豆は、一般的にほぼ黄色く枯れ落ちているのですが、この場合はどうでしょうか。
最後の力を振り絞ってエネルギーを熟して欲しい。
祈る気持ちです。
自然農の見学会・12月はお試し体験もあります
待ったなし、という言葉がいつも脳裏にあります。
気候は変わり、世界はどこか変な方向にシフトをする。
冷暖房に包まれた室内で情報空間に浸っている生き方には、いつか破綻が来ます。
いまだからこそ確かなものは、自分が五感で感じる世界です。
感性を取り戻す。食を取り戻す。
そんな生き方に、少しづつでもシフトしていきましょう。
「さとやま農学校」は、ほとんどが首都圏・都会暮らしの方々です。
農業の経験はないけれど、都会での暮らしから自給自足への一歩を踏み出したい。
そんな想いを抱く方々の集う場所として、2026年は13年目の活動に入ります。
「どんな場所だろう?」
「自分に通えるのかな?」
と、興味を持ってくださった皆さん。
どうぞ、一度おいでください。
11月は十種の様子をご覧いただけます。
12月は、実際にお試し体験をしましょう。
詳しくは下のリンクをご覧の上でお申し込み下さい。