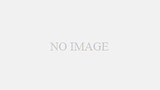こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
写真は「自然農を学ぶ・さとやま農学校」の農園の片隅です。
畝の中に、エビスグサが生えています。
相模湖では冬に刈れてしまう一年草なのですが、生長が早くて、放って置いたら2m近くなることもあります。これからの猛暑を考えるときに、畑はできるだけ立体化して日陰を作り、できるだけ不耕起にして多様な生き物が身を守る場所にしたい。
トラクターでサラリと整地してしまうと、太陽を避けてミミズも微生物も逃げてしまう。
今年のような日照りになれば砂漠になる。
人類史のなかで、農耕が作り出してきた砂漠は、今なおまた新しい砂漠を作り出す危うさを秘めているのです…ちょっと控えめに書いていますが、日本は比較的、雨に恵まれているので放棄されたとちでも、やがて緑が覆います。しかし、この先は?どうでしょうか?年によっては、極端な乾燥も増えることでしょう。その結果、膨大な水と生命が、土から失われていきます。
二酸化炭素を植物が固定するという意味でも、不耕起栽培は理にかなっているのです。
ただし「さとやま農学校」では、何が何でも不耕起にすべしとは、教えていません。不耕起の段階に持っていくには、やはり段階があります。そのあたり、詳しくは実際に土に触れながら学んでいただきます。頭から「こうあるべし」と学んでしまうと、融通が利かなくなるのです。

エビスグサの株元にカラシナのこぼれ種が群生しています。
暑い最中でも、こんな1mほどの緑陰があるだけで、育ちも違うようです。よく見れば、エビスグサの子供たちも芽を出しています。小さな森の様です。
「さとやま農学校・秋のショートコース」では、こうした場所でタネを蒔きます。単にバラまくだけでなく、そこはある程度手を添えますが、基本形を読みながらの手入れです。
畝には多少の凸凹もありますが、それもまた意味ありとします。
均一の野菜を一斉につくるならば、畝はしっかり耕して均したほうが効率が良いですが、自給の場合には、むしろこうした不均一の中に調和を作っていくイメージです。
宇宙のビッグバンでは、宇宙空間に拡散するガスの濃淡があり、濃い部分が星雲になったと聞きました。ガスのムラ(=濃淡)があればこそ、生まれてくるものがある。これまで土をあまり触っていない人には、そんな自然界の生成のダイナミズムを感じて欲しいところです。

これだけ沢山生えていても、すべてが大きくなるわけではありません。
弱いものは虫に食われて土に還ります。
それがまた栄養分になって仲間を支えていくことにもなります。
弱肉強食というよりは、命が支えあう関係ですね。
毎年毎年の光景ですが、いくら眺めても、なんだか不思議です。
「センス・オブ・ワンダー」
自然界を見て、不思議だ・面白いと感じる気持ち。
都会では失いがちな感覚を、取り戻しましょう。
「自然農を学ぶ・さとやま農学校の見学会」
9月から再開しました。
どうぞ現場の雰囲気を感じてください。
本講座の受講生の皆さんの声も聞けます。
公共機関でおいでの方は送迎もします。