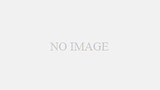~いつもながらに芸術的な造形~

おはようございます。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
今年もコンニャクの出てくる季節になりました。
何十年も前に、はじめて借りた畑の片隅にこれが出てきたときは、何事かと思いました。
そうして随所を見れば、里山の各地で、果樹園や茶畑の隙間、ときには墓石の裏からコンニャクが出てくることがあります。
コンニャクは、これから葉っぱを広げるのですが、どんな生育ステージでも絵になるのがコンニャクです。
そして冬になって掘り上げるコンニャク芋は、黒くて重くて、もちろんそのままではエグくて食えません。
そのイモの皮を剥いて、茹でて、すり降ろして灰でアクを抜いて固めて水にさらすという手の込んだ段取りを、いったい誰が考え出したのか?
おそらく我々の祖先は、色々な植物を目につく限り口に入れ、それで死んでしまった人もいることでしょうが、そうした膨大な試行錯誤のなかから、いまのようなコンニャクづくりが出来上がったのでしょうけれど、それでありながら栄養的にはほとんど価値がない。
人類の食に懸ける情熱には、時として説明しがたい不合理があるのだと、コンニャクは教えてくれます。

コンニャクが葉を伸ばしているところ。
アートですね。

立派に葉を広げています。
芋が大きいほど地上部も太くて立派です。
自然栽培のコンニャクの育て方
コンニャクは、地下部のコンニャク芋の上に「生子(きこ)」と呼ばれるものができます。
これを食べずに、芋からぽっきり外して埋めておけばまた2,3年かけて食べごろのコンニャク芋ができます。栽培農家は、こうして年生を揃えて栽培管理します。
いっぽう自然生(ジネンバエ。ジネンジョウ)と呼ばれるものは、まさに自然界そのものに、色々な年次のコンニャクが混ざり合って育ちます。全く自然状態のコンニャクは、南西の斜面に生えていることが多いそうです。そして分厚く落ち葉や枯草などの表土のもとで育つのだそうです。異常は、栗原浩先生(九州東海大学)の論考から引用させていただきました。
気候変動の中で、自給自足への一歩をはじめましょう
梅雨らしい梅雨は今年もなく、時折降ってくる雨は警報級の豪雨です。
アメリカでは数日前に起きた洪水で100人以上の死者が出たものの、米国政府は「気候変動はない」として、政府のキャビネットに、さらに気候変動に否定的な学者を加えるという姿勢を続けています。
人類そのものが壊れかかっています。
そして地球も厳しい。
でも、まだ地球にも人間にも希はあります。
頭の中で憂いているばかりでなく、まずは大地の上で出来ることを始めましょう。
猛暑ではあるけれど、できることは人それぞれにあります。
使命感とか義務感というのを先立たせるのでなくて、手を動かすことの愉しさ、あるいは小さな命が育つことの酢バラ歳差をしみじみと味わってください。
国分寺で開催する「自然農のプランター栽培講座」は7月、8月ともおかげさまで満員になりました。
皆さんの関心の高さを感じます。
そして9月からは毎年ご好評を頂いている「秋のショートコース」を開催します。
9月から12月まで月に1回=合計4回の講座です。
さとやま農学校の本講座でも大人気の「かまどご飯」もあります(希望者のみ・別途有料)
ショートコースが終わる頃には皆さんのつながりもできて、冬の「味噌づくり」や「餅つき」その他もろもろの農学校の会員限定イベントにも参加できます。あるいは皆さんがイベントを企画するのもOKです。
自給への一歩というのは、もちろん技術的なことが基本ですが、いま分断されている人間同士のつながりを、程よい程度につなぎ直していくことも大事です。そんな感覚が見えてくるのも、こうした講座の良いところですね。