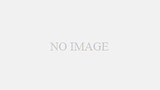こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
9月3日。
台風15号の到来を目前に「自然農を学ぶ・さとやま農学校」の臨時活動でニンジンの種を蒔きました。
もう何度目かのニンジンの種まきです。。
昨年も猛暑で苦戦しましたが、今年はなお手ごわい。
原因はひたすらシンプルで、とにかく高温と日照りです。
ニンジンの好む適正な温度を上回り、さらに梅雨も含めて雨がない。
その証拠(?)に、日陰のプランターに蒔いたニンジンは、下の写真のようにスックリと発芽しているのです。当たり前と言われたらそれまでですが。


6月に蒔いたときのように裸足で転圧するわけにもいかず、今回はスベリヒユを刈りながら、
タネを蒔いてはカマの背で叩いていく方式です。
つくづく今年の経験で感じたこと:
その1)ニンジンの作型を春まき(初夏どり)と秋まき(春どり)のふた山に代えていく。
つまり、今までのような梅雨を当て込んだ6月~7月上旬の種まきでなく、お盆を過ぎてから9月前半の間に蒔く。そのかわり、年内の収穫はあまり期待できない。
その2)高温乾燥は織り込んで、芽だし(プライミング)をしっかりして蒔く。
ということです。
「種まき」の前にひと手間かけて「芽出し」をすることが今まで以上に必要になります。
なので、芽出し処理をして種を蒔く、というのを、来週からもう一回「さとやま農学校」で実践します。試行錯誤は最良の教科書です。
固定種キャベツのスーパーセル


7月にタネを蒔いてスーパーセル育苗したものです。下の葉が赤く色づいているのは、スーパーセルの特徴でもあります。厚くなって強い葉です。
ただいま小さな体で、酷暑に耐えてくれています。いったん露地に定植した野菜に水を上げることは滅多にないのですが、今朝は特例として水を上げました。後は雨ごい。
明日はようやく雨雲が来そうな気配ですが、やっぱり来ない、ということが関東平野ではよくあります。
二枚目の写真は、防虫ネットの上にホワイトの遮光シートを駆けました。
光りは通して温度を下げるというものですが、あくまでも育苗などで使うものです。非常に高価なので、畑で使うことはありませんが、今回は特別。商品名はクールホワイト。
これから週をまたいで、残りのキャベツやブロッコリのスーパーセルを少しづつ定植していきます。
そして彼岸にかけては種まきラッシュです。皆さんも、タネの準備は大丈夫ですか?
秋の種蒔きは、ツボをはずすと初夏まで畑が寂しくなります。
こんな気候変動の時期ですから、一つのやり方では失敗することもあります。
農家さんは、それぞれ工夫を凝らしていますが、ことさらに特別な資材を買うことはせずに、身の回りのものと、隙間時間を活かした「芽出し」をしています。
つまり、種まきと言っても直に蒔くばかりでなく(自然農はそのイメージが強いのですが)、手元で「芽をださせる」ところまで一手間かけて、面倒を見てから畑に送り出すのです。

上の写真は、昨日9月4日。
台風15号の雲が関東まで前線を広げて、折々に雨がパラつきました。
涼しいというか、やや蒸し暑いけれど、直射がないと動きやすいですね。
この日も臨時活動で、ひたすらハウスでタネを蒔きました。
メインはタマネギです。
極早生と晩生の2種類。
タマネギや長ネギも、種まきの仕方は色々ありますが、今回は写真のように小さなセルトレイにタネを蒔き、その上に小粒の赤玉を重しのように載せました。
少し重量ストレスをかけることで、タマネギのような単子葉植物は、しっかりした芽が出てきます。

前のブログでも書きましたが、初心者が畑を始めるなら「春より絶対に秋」です。
「さとやま農学校・秋のショートコース」は、初心者の方が種を蒔いて収穫するまでのベーシックを学びます。4回の講座にエッセンスを詰めて、さらに学びたい方は、本講座に進んでいただけます。もちろん本講座に初めから参加するのもOKです。