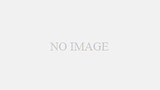オーガニックの菌床キノコ

こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
まずは10年前の写真から。
オーガニックの菌床キノコです。
色々な種類があって、どれも美味しいものでした。
2枚目はキノコの栽培現場です。無言のキノコたちのオーラに包まれました。

このオーガニックのキノコは東京・多摩の恵泉女学園短期大学の澤登先生が開発されたものです。
(残念ながら同短期大学は、2024年に学生の募集を中止し、数年後に閉学の予定だそうです)
昔ながらのシイタケの原木栽培は重労働なので、現在の主流は、樹木のチップ(菌床)にキノコを植菌する「菌床栽培」ですが、コバエなどの発生を防ぐために菌床に薬剤処理をするのが一般的です。そのためにオーガニックのキノコは、当時は日本にはありませんでした。だから有機JASもキノコは認証の対象外だったと記憶しています。
キノコを育てた後の菌床は、菌床のセルロースやリグニンなどが食いつくされてスカスカになります。これを「廃菌床(はいきんしょう)」と言います。土に還りやすい状態です。
さて。
この写真よりも数年前に「炭素循環農法」の林先生がブラジルから来日されて、勉強会が神奈川でも開催されました。今の「菌ちゃん農法」も、この炭素循環農法を元に発展されたと聞いています。
簡単に言えば、窒素を含む肥料は一切使わず、大量の炭素源を、不耕起で畑に敷いていくというものでした。その点、廃木はボリュームがあって土に還りやすいので、炭素源としては非常に有効です。
周囲の有機農業のお仲間は、こぞって原木栽培のシイタケ農家さんに使用後の原木を貰いに駆け付けたものでしたが、やはり原木は重い。
いっぽう、こちらの廃菌床はコンテナで運べるし、ホロホロと分解されているので扱いやすい。
私は何度か大学に通って、廃菌床をハウスの一面に敷いたのですが、ハウスに入るとキノコスープのような美味しい香りがしたものです。

なんでこんな話をしたか。
今日はウメの果樹園で草刈りをしていたのですが、スギの丸太に、サルノコシカケみたいなキノコが生えていたのです(写真3,4枚目)
スギは静かにキノコに分解されて、土に還り、いつかウメになるのでしょう。
自然農の畑では、色々なイノチがお互い同士に形を変えて循環しています。
私はこれを「イノチのやり取り」といっています。
何だかヤクザ映画のようですが、でもそうとしか言いようがない。
今ここでスギであり、キノコであり、ミミズであるお互いそれぞれは、イノチをやり取りしながら、お互いの姿を「取り替えるっこ」しているのでないかな。そんな風に思えます。
その取り替えっこの巡りの中に、本当はヒトも入るべきなのですが、ヒトの排泄物は、食物連鎖の最上部として有機水銀が濃縮されていて、循環させるには問題もあるようです。
この10月は、雨が細く長く降っていて、農学校にもキノコがチラホラ生えています。
そんな「イノチのやり取り」を「さとやま農学校の見学会」でご覧になりませんか?

見学会は2025年12月3日まで開催しています。
実際の講座の様子を垣間見ることができます。
最寄りのバス停まで送迎あります。
車の方には駐車場もあります。