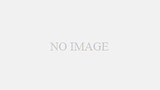こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
「自然農を学ぶ・さとやま農学校」の皆さんと、冬どりタマネギの植え付けをしました。
タマネギは、本州での作付けは、秋にタネを蒔き、冬の初めに苗を植え付けて、翌年の梅雨前に収穫します。タマネギは多雨が苦手です。
そのため、年明け早々は九州などからタマネギの出荷が始まります。
やがてブランドチカラの在る淡路島など、さらに関西から関東へと産地が移ります。
タマネギの国内最大の産地である北海道の作付けは違います。
春にタマネギの種を蒔き、秋に収穫です。
当然、品種も、違うものになります。
その辺は日本農産というメーカの独壇場なのですが十年ほど前に、これまでの来ない程の大規模な台風が北海道を襲いました。いわゆる「蝦夷梅雨」と葉別次元のものだったようで、これがタマネギの産地を直撃し、さらに本州向けにタマネギの苗を出荷している産地も打撃を受けました。
あの時のことは今も覚えていますが、こちらでも、苗がなくて、種苗屋さんやホームセンターは大変なことになったのです。
気候変動で北海道にも梅雨が来るようになり、冬のタマネギを北海道にばかり頼らずに自分たちでも、という機運が出てきました。タキイ種苗が春まきタマネギ「シャロム」を開発したのが、それに先駆ける頃だったかと私は記憶しています。「現代農業」が毎年2月号で特集する品種特集でも紹介されました。
春に蒔いたタマネギを、まだ小さな球の段階で梅雨入り前に掘り上げて日陰の涼しい場所で保管します。その間、小球は休眠し、秋に植え付けて冬に収穫する。
これは長ネギの干しネギと同じつくり方ですね。

冬どりタマネギができれば、家庭菜園でも、冬に新鮮なタマネギを食べることができます。
ただし、短い期間でタマネギを成長させるには、それなりに土が肥えていることが必要です。
無肥料栽培の場合、肥料でプッシュして育てる形ではないので、小ぶりのタマネギになりがちです。ちょっとペコロスみたいな。でもそれはそれで美味しいものです。ジャガイモでもタマネギでも肥料で大きくした2Lや3Lサイズは水っぽいです。

冬に備えて地温をキープするために穴あきマルチを使いました。
普通、このマルチはトラクターを何度かかけて、粉々にした土の上に張るものです。
そうでないと、ご覧のように凸凹して、下手をすると草が突き出してきた理、穴と地面に隙間が空いて、そこから風が吹き込んだりします。木枯らしの突風の時には、それでまくり上げられることもある。ですから、慣れない人はマルチをピン止めすると確実でしょう。
いっぽう、タマネギの種蒔きも済みました。
こちらはハウスで育てています。
ニンジン、タマネギ、ジャガイモのいわゆる「カレー御三家」は、自給菜園でもきっちり育てたいものですね。ジャガイモはつつがなく育ちましたが、今年も日照りでニンジンはやっと今発芽が揃ったところです。そしてタマネギと。
こんな感じで季節は秋を迎えました。
そして、すぐに冬が来ます。
冴え冴えと高い、冬の空が好きです。
「さとやま農学校の見学会」
10月も引き続き開催します。
実際の実習の様子をご覧いただけます。
「自然農って、自分でもできるかなあ」とお考えの方、まずはおいでください。
受講生の皆さんの話も聞けます。
公共機関の方は送迎します。
車の方には駐車場があります。