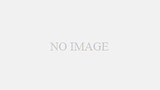こんにちは。
神奈川の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
写真は、ありふれたカラムシ(苧麻)です。
夏草の代表ですね。
競争力が強いので、今の季節は道路に溢れるように覆いかぶさる常連です。
苧麻の繊維を細い糸(麻糸)にし、膨大な手間をかけて織り上げたものが上布(じょうふ)。
私がかつて住んでいた宮古島の「宮古上布」も、さらっとした肌触りが素晴らしい高級なものでした。
宮古上布は、大変に熟練した技術と時間を要するものだったので、今も後継者が少ないと聞きます。高級品として販売できても、それを職業として食べていくのは大変なようです。

二枚目の写真は、その宮古島で苧麻から糸を績(う)んでいるところ。
上布として織る以前に、こうして糸を績む作業があります。これがまた熟練を要する作業だそうで、織り以上に後継者不足に悩んでいました。宮古島ではタカラガイを使って苧麻の茎から糸を績んでいました。
いつも思うのですが「衣食住」のうちで一番自給が大変なのは衣の分野でしょう。だから古より、衣類は物税として納めさせた。
宮古上布は、かつては権力者が税として強制的に納めさせました。作業小屋に女子を幾人も監禁するような過酷な環境で作らせた様子が、島の博物館にも展示されています。
夏の盛りには全国で見渡すかぎり生い茂る苧麻(カラムシ)は、だから繊維として有効利用などというのは、なかなか難しいように思えます。でも、カラムシの草刈りにかかる労働力と刈払い機のためのガソリンは膨大です。
ヤギを飼ってカラムシを食わせるというのが本来は自然なのでしょうが、個人的にヤギは、あの目つきと鳴き声がどうしても好きになれません。
昨年からは、風の草刈りを少しづつやることで、旺盛な伸びは収まりました。地面が見えるような草刈りは、地温が上がるばかりで、その後のリバウンドもひどく、この時代にあっては地温を上げない高刈りが良いのですが、なかなかそこまで頭を切り替えるのは難しいようです。
土用が明けたら立秋です・秋から自然農の一歩を
四季折々の「土用」とは、私はおもうところ、農民にとっては骨休めのための後付けの理屈だったのではないでしょうか。土公神が休めるように、土用の間は畑を耕さない・・・つまり人間も休みたいのだということですね。
そんな土用が明けたら立秋です。
どこが秋?と思うのは当然ながら、その秋に向けての準備を構える季節です。
とくに植物は、秋一日と遅くなるにしたがって収穫も遅くなる。
しかし一方で、夏が暑くなったために、初心者が畑を始めるのなら、むしろ秋がお勧めです。
ゆっくり感じる時間があります。
冬も、かつてほどの厳しい寒さではなくなりました。
(霜柱を見なくなって何年になるでしょうか)
まずは自給への一歩を踏み出しましょう。
詳細とお申し込みは下のフォームからどうぞ