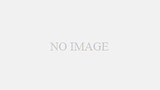こんにちは。
ちょっとブログをご無沙汰したつもりが半月も・・・本当に月日は早い。
「さとやま農学校2025・秋のショートコース」の模様です。
9月の1回目に蒔いた「カツオ菜」の様子。
10月は雨が多くて日照が少なかったのですが、元気に育ってくれました。
かつお菜は福岡の在来野菜です。カツオのような旨味があるというところから、この名前がつきました。お汁に入れると、確かに滋味があります。これとアゴダシで雑煮というのが、ご当地の定番なのでしょうか。東京に昔の雑煮は、鶏肉とコマツナ程度の質素なものでしたから、羨ましい。

9月開始のショートコースではハクサイの代わりに山東菜を蒔きました。
結球しないハクサイ、という位置づけです。
収量はもちろんハクサイの方が多いのですが、作りやすさでは山東菜、あるいは同じ仲間の「べかな」「大阪しろ菜」などの方が作りやすいですね。大きなものから間引いていきます。間引いた後は、さらに別のものを蒔きます。間をあけたら畑が勿体ないです。
隙間を作らず、次の作物を間断なく仕込めるのが不耕起栽培の良いところ。

今年は日照りでニンジンの発芽に難儀したので、ルッコラを蒔きました。やがてルッコラの影に隠れてニンジンが芽を出しています。太陽があたるようにルッコラを間引く。そして収穫ばかりでなくて、夏の草が枯れて腐植となった土を畝に寄せます。とくに堆肥は作りません。太陽のエネルギーが植物になり、それが枯れて土になってまた植物になる。あるいは表土として蓄積される。とてもシンプルな仕組みです。無理なく、それほどのチカラを使わずに自然農で続ける自給。
「農学校・秋のショートコース」は既に締め切っていますが、「さとやま農学校」の本講座は、いつからでも参加できます。近年の温暖化で、野菜づくりを始めるのはできれば秋から、そうでなければ冬のうちから準備をすることが大事になってきました。「さとやま農学校の見学会」は、11月は実習の様子を見学できます。そして12月は、お試し体験ができます。「どんな場所かな?」と思う方は、どうぞおいでください。