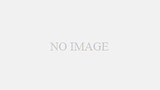こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
「自然農を学ぶ・さとやま農学校」は、夏の盛りは講座の回数を減らしています。
そのかわり、希望者による臨時の活動があります。
9月1日は午後の、日差しが弱まるタイミングで作業を始めました。
朝の畑も良いものですが、夕方の畑も風情があります。
ヒグラシがちょっと寂し気に鳴き、トンボが飛び交う。
上の写真、奥の方が暗くなっているのが分かりますか?
山の端から日が暮れているのです。
ここから15分ほどで、畑も陽が暮れました。
太陽が隠れるだけでぐっと涼しくなります。
ここがコンクリートの都会だと、真夜中でもモワっと暖かい。
熱帯夜の所以ですね。
でも畑でしっかり汗をかくと、だんだんと帰りはクールダウンしてきます。
良い汗をかいて、夏をやり過ごし、秋を迎えたいですね。


臨時活動なので、普段はできないような作業を取り入れます。
そのひとつが、マメ科の植物を漬け込んだ緑肥(液肥)づくりです。
写真にあるのはエビスグサ。
薬草茶の「ハブ茶」として売られているのは、多くがこのエビスグサだそうです。
熟したこげ茶色の種は、煎じると甘いお茶になります。
だいぶ畑の随所に増えているので、その一部を刈りこんでタルに詰め込み、水と土をかけて、
フタをしました。
まるで漬物ですね。
とってもシンプルなコンポスト
これは伝統的な手法です。
マメ科の青草と畑の土と水だけ。
いま伸び盛りのマメ科の草は、冬には枯れて土に還りますが、そのときに窒素成分の一部は空気中に放出されます。そうなる前に液肥として使いまわすのが昔の人の知恵です。
自然農を続けていれば、土は整ってくるので、こうしたものも不要になるのですが、始めたばかりの畑など、場合によってこうした技術も役に立ちます。
使い方のポイントは:
・施用する相手(作目)を選ぶ。
・醗酵の様子を五感でチェック
・施用の仕方を気を配る
というところです。
水が多めなので、醗酵の具合はこまめにチェック。米ぬかボカシが「甘酒」のような香りでスタートするのに比べて、こちらはたんぱく質が多いので、クセのある臭いです。
このように、本来、農業と醗酵は不可分の関係にあります。
畑の土の醗酵、
台所の醗酵、
そして体内の醗酵と代謝。
全部つながっています。
そのつながりが感じられるのが農業の愉しさ。
生きていることが実感できます。
猛暑と冷房で干からびちゃった方。
秋からの畑においでください。
「さとやま農学校ショートコース」
10月からも参加できます。