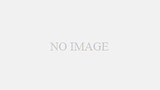こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
写真は「自給の自然農を学ぶ・さとやま農学校」のナスです。
ナスは「すどう農園」が新規就農して始めに手がけた野菜のひとつでした。
「顔の映るほど艶があってピカピカのナスをつくりなさい」
というのが、生前にお世話になった、お師匠様の言葉でした。
今は雨がないので、育ちもゆっくりですが、高温乾燥で出やすいダニにも負けないナスです。
何年もこの環境で種取りをしているからでしょう。
20年以上前に、初めてナスをつくったときは市販の接ぎ木の苗も使いました。
しかし、何不自由なく育てられた苗は、高温乾燥に弱いものでした。
すどう農園は農業用水がないので、あっという間にダニが出た。
当時は、数百本のナスを作っていたから、十分な水やりなどは到底無理で、いま想えばそんな作付けをした方が根本的に間違っていたのですが・・。
自然農の畑では、水は下から来ると考えます。
まず大事なのは地中の水をしっかり吸い上げる逞しい根。
それをサポートしてくれるのが菌であり、両者の共生エリアである根圏を育てること、土中環境を壊さない事が肝要です。
「自給の自然農を学ぶ・さとやま農学校」でのナスづくりは、ひたすら同じ場所で、耕さずにナスを育てています。もちろん種は、同じ場所で採れたタネを使います。
私の好きな作家・藤沢周平さんは、ナスがお好きと見えて、作品の中にしばしばナスが登場します。
直木賞を受賞した「暗殺の年輪」では、庭先のナスに朝・昼・晩と、柄杓で水をあげて柔らかいナスを作るのだと書いてありました。舞台は江戸時代の武家の家ですが、これが伝統的なナスの作り方。
まあ、ナスのことは措いても、これは珠玉の短編ですよ。藤沢さんの作品には、ご出身の山形の風土がきめ細かく描写されています。この辺りは今どきの時代小説には、なかなかないですね。
必ず図書館にあるので夏の読書にお勧め。
ちなみに、畑で暑いとき、糖度の高いトマトを食べるとかえって喉が渇くので、むしろナスを齧るのが良いですね。
自然農の自給は秋のスタートをお勧めします
初心者の方は、春先に畑を始めると、急な気候の変化や野草の勢いに圧倒されがちです。
とくに自然農の場合は、周囲の草や虫や、風とどう関係を作るのか、その呼吸を取るのが難しいのです。それを考えるとむしろ、これからの野菜づくりは、秋のスタートを考えるのが無理がないです。
8月は「自然農のお試し体験」
9月以降は「さとやま農学校見学会」があります。
そして9月からは「さとやま農学校2025・秋のショートコース」
10月からは本講座の受付と、秋冬に向けてエンジンがかかってきます。