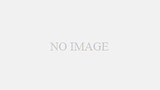こんにちは。
神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。
あきたこまちの出穂です。この写真は2025年7月28日のものです。
「さとやま農学校」の一角にある、樽に土を入れて水を張っただけのものです。
先日のブログでご紹介した「国分寺の古代赤米」よりはだいぶ遅れての出穂です。
あきたこまちの籾は「さとやま農学校」の卒業生で、現在は秋田県にご夫婦でUターン就農された田口さんご夫妻に頂いたものです。今年は2年目の田んぼに取り組んでいるところです。
ご存じの方も多いでしょうが、秋田県は今年度から県をあげて従来の「あきたこまち」から放射線育種された「あきたこまちR」に転換することを決定しました。
そうすると、どうなったか?
従来の「あきたこまち」を作りたくても作れない。
ここは説明が必要です。
別に従来の「あきたこまち」をつくってはいけない、などという法律はありません。
自分で採集した籾を使えば、また作れます。
しかし、生産農家として「あきたこまち」を作ることは、事実上ほぼ無理です。
秋田県下のJAは、もう従来の「あきたこまち」の取り扱いをしません。
JAが扱わないということは、事実上売り先がないのです。
JAをすっ飛ばして相対で小売業者に米を売れる農家は、一部です。
とくに秋田のような大規模生産のコメどころはJAあってのコメづくり。
米というのは、非常に集権的な作物なのです。かつてはお金だったし。
繰り返しますが「事実上」というところが大事です。
かつての「あきたこまち」をつくるな、という条例は秋田県にもありません(当たり前だ)
しかし:
「自分だけ従来のあきたこまちをつくります」
というような態度を取れるかどうか。
たとえばコロナのワクチンを想像してください。
コロナのワクチンも、接種を義務づける法律はありません。
しかし「自分だけワクチンを打たない」と言えない職場も多いわけですね。
同じような同調圧力の空気は、農村ではまだまだ凄いのです。
我々の先輩の有機農家の方々が、かつて「自分の田んぼだけは農薬散布をしない」
と主張したときに、どれほどひどい仕打ちを受けたか。
まあ、今だってそうした地域は残っているでしょう。
放射線育種の何が問題なのか
・放射線育種とはどのようなものか・何が問題か?
・なぜ秋田県は「あきたこまち」の放射線育種を進めるのか?
・国の農政はなぜこのような動きを後押しするのか?
・秋田県の生産農家にとって、何が問題か?
これらについては「すどう農園」も参加している「OKシードプロジェクト」が、精力的に調査と広報活動をしています。その貴重な情報は、ほぼ無料で公開されています。
代表の印鑰(いんやく)智哉さんは、一昨年から昨年にかけて国分寺のカフェスローで「食のクライシス」というシリーズ講座を開催しました。
まず、詳しくはOKシードプロジェクトのサイトをご覧ください。
そして支援会員になってください。
そもそも、それ以前の事として:
種苗に関すること以外にも、今どきの科学技術全般が、非常に先端的になり、一部の専門家にしかわからない(コロナを巡るワクチンや原子力発電所のことなどは最たるものですね)。
しかも、専門家は、専門の事しかわからない。分かろうとしない。
自分の関わる分野のことが、いずれ社会全体にどんな影響・リスクを及ぼすのかが分からない。あるいは分かろうとしない。
これまでは秋田県が「あきたこまち」を開発し、そして秋田の誇るブランドとして育ててきた「あきたこまち」へのサポートをすべてやめて「あきたこまちR」一本に絞った。しかも令和7年度産の「あきたこまちR」から始まって、今後はすべて名称を「あきたこまち」にするということです。
つまり従来の「あきたこまち」と見分けがつかなくなってしまったのです。
もちろんこうした事情を知っていれば今年令和7年度からの秋田県産の「あきたこまち」が昨年までの者とは違うと分かります。だから旧来の「あきたこまち」を食べたければ、例えば茨城県などの「あきたこまち」を選べばよい、となります。食を巡る情報は、大手にメディアではほとんど取り上げられません。
スポンサーの多くが食品企業あるいは化学企業やその系列だからです。
国(農水省)の中には食の安全にかかわるセクションもあるのですが、そうした部局には食品企業からの出向がいるなどして、むしろ企業サイドに立った部局となっています。アメリカの政権と企業との関係では「スイングドア」と言いますが、同じような関係ができることで、官僚の側にとっても天下り先の確保という面もあるのでしょう。
まずは手を動かそう
今日のような話題は、どうしようもなくめげてくるものです。
孤軍奮闘しているOKシードの印鑰(いんやく)さんには本当に頭が下がります。
我々のように土に触れられる人間は、こんな時はとにかく土に触れてノイズを放散します。
日中の暑さも、3時を過ぎれば和らぐものです。
土の上には、言葉を越えた不変があります。
黙って手を動かすことは、今の時代だからこそ、なおさら大事になってきます。
全くの初心者の方、都会から一時リフレッシュしたい方、どうぞご参加ください。